
計算論的精神医学入門:山下 祐一(国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第七部 室長)
現行の精神障害の診断分類は、患者自身の主観的報告と医師による行動観察に基づいており、生物学的知見・病因・病態生理に基づいた体系になっていない。また、近年の生物学的知見の蓄積によっても、診断、重症度評価、予後や治療反応性予...
応用脳科学アカデミー

現行の精神障害の診断分類は、患者自身の主観的報告と医師による行動観察に基づいており、生物学的知見・病因・病態生理に基づいた体系になっていない。また、近年の生物学的知見の蓄積によっても、診断、重症度評価、予後や治療反応性予...

脳科学分野は急速に発展しています。それにより、わたしたち市民は脳科学研究の恩恵を受けることができます。しかし、それと同時に、わたしたちは脳科学研究の成果がわたしたちの従来の社会や人間観にどのように影響を及ぼすのか、吟味す...
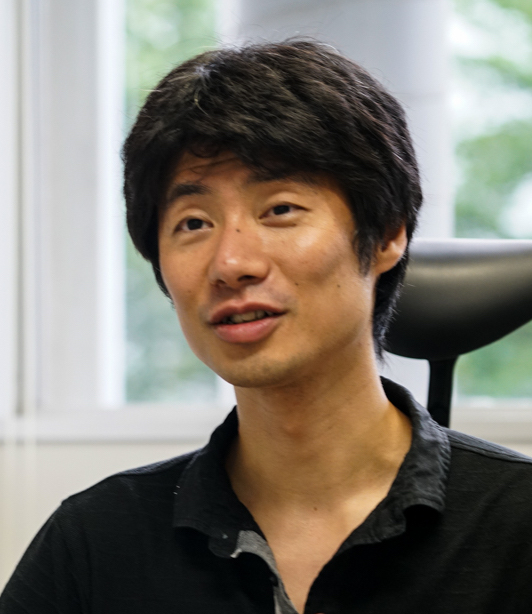
我々の適応行動は、脳内で発現する「活動依存性シナプス可塑性」というメカニズムによって支えられており、新たな経験を通じて脳は環境情報の表現を学習します。本講演では、生物学的制約条件下において脳がいかに抽象的・確率的な情報表...

脳・神経科学技術の急速な発展と、そのデュアルユース(軍民両用)的特性がもたらす新たな認知戦・情報操作戦略の展開について検討する。とりわけ、中国人民解放軍内で台頭する「制脳権」概念、米国で議論される「マインド・ウォーズ」や...

fMRIをはじめとする脳イメージング技術の発展によって、ヒトの内観を驚くほど詳細に調べることが可能となりつつあります。一方、脳イメージング技術には実験デザインや解析に種々の制約があり、その解釈には注意が必要です。本講義で...

消費者の知覚や記憶、選好や意思決定は人間の情報処理(認知)プロセスそのものであるため、消費者行動を科学的に理解するためには認知心理学的アプローチが有用である。本講義では、まず認知心理学の基本的考え方を解説し、フィールドで...
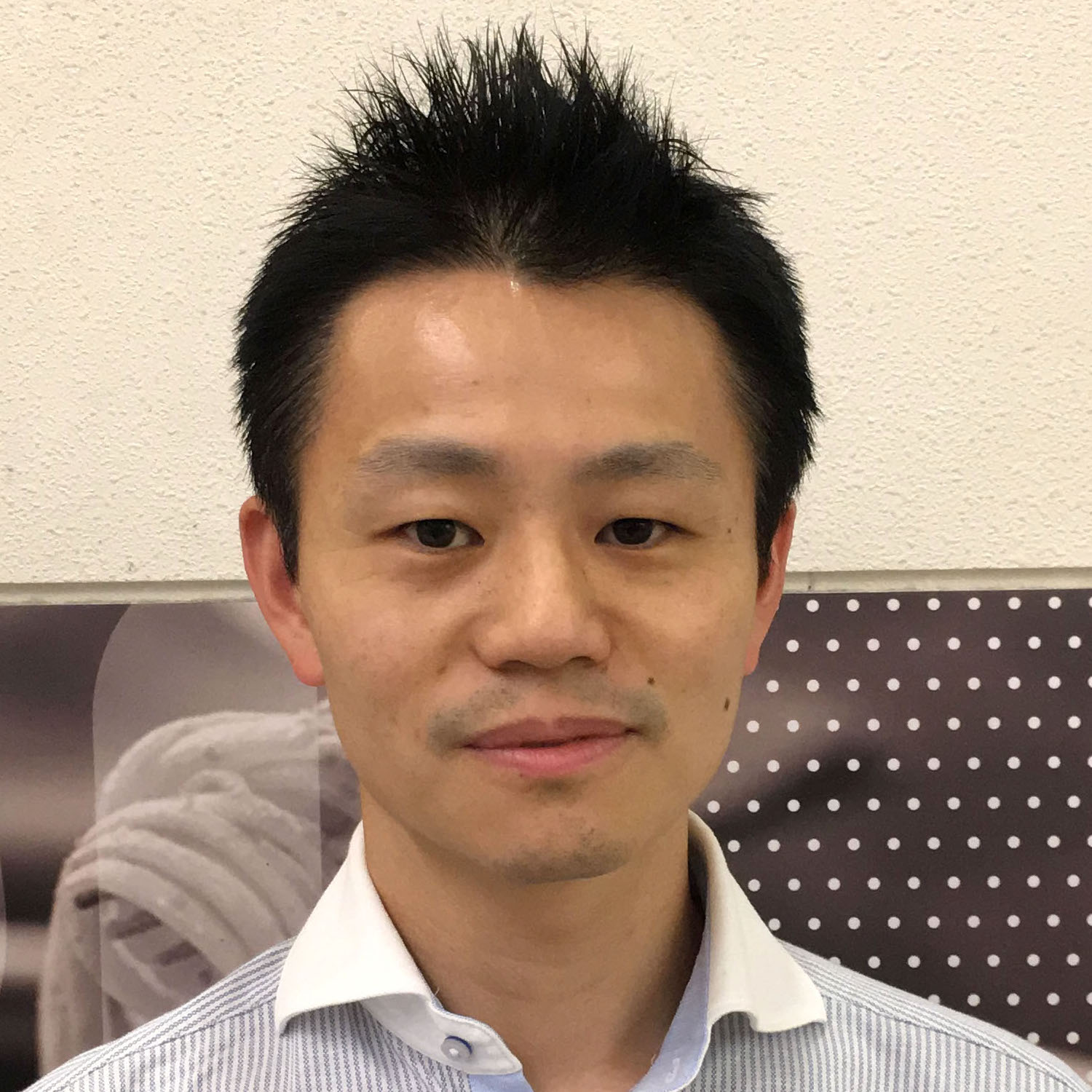
2016年以降、嘘やデマ、陰謀論やプロパガンダ、こうした虚偽情報がソーシャルメディアを介して大規模に拡散し、現実世界に混乱や悲劇をもたらす事象が次々と発生している。さらに近年では、生成AIの台頭により、虚偽情報が高度化・...
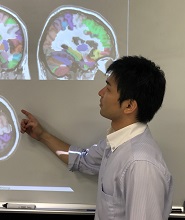
昨今、ディープラーニング(深層学習)から端を発し、アルファ碁等の登場によりAIブームが巻き起こっており、その技術はスマホ、家電、セキュリティに至るまで様々なものに転用され、もはや身近なものになっているかと思います。一方で...

さまざまな分野で,パーソナルデータをはじめとした大量のデジタルデータを流通させ,利活用してイノベーションを創出することが期待されています。一方で,データの取り扱いの拡大に伴い,データ利用にかかわる倫理的・社会的問題も顕...

最初に、新規科学技術の研究開発から社会実装までを「倫理的・法的・社会的課題(ELSI)」という切り口で検討することの意義について考察します。特に、パーソナルデータを利活用する、すなわち、データを取得し、学習済みモデルを作...