
応用行動分析学をベースにした自閉スペクトラム症への支援と未来:井上 雅彦(鳥取大学 医学系研究科 教授)
「自閉スペクトラム症(ASD)って何?」「どんな治療法が効果的?」「親や支援者にできることは?」そんな素朴な疑問からASD支援の現状と未来について考えます。本講演では、エビデンスのある支援方法であり、行動科学の一つである...
応用脳科学アカデミー

「自閉スペクトラム症(ASD)って何?」「どんな治療法が効果的?」「親や支援者にできることは?」そんな素朴な疑問からASD支援の現状と未来について考えます。本講演では、エビデンスのある支援方法であり、行動科学の一つである...

これまで感覚ダイバーシティ・感覚過敏の多くは見過ごされ、社会的にはネガティブな事象として扱われてきました。当事者やその家族は生きづらさを強いられてきました。しかし、感覚ダイバーシティ・感覚過敏を科学として取り扱うことで...

脳は外界からの情報入力から中枢神経系を経て行動を発現させるまでの情報処理を驚くほどの速さで行っているが、外界の情報は膨大かつ曖昧であり、脳の能力も世界を正確に表現するには絶対的に不足しているように思われる。にもかかわらず...

我々が創造性を発揮できる背景には、どのような認知・神経メカニズムが存在しているのでしょうか?我々の意識や意識下で起こる過程は、創造的なアイデアの生成にどのように貢献しているのでしょうか?これらの疑問へ迫るべく、本講演では...

感性というキーワードがモノづくりの領域に取り入れられて久しい。一方で、モノづくりにおける感性とは、ユーザーのスキルを指すのか、ものが持つ機能・性能を指すのか、明確に定義できていない。一般的には、感性とは美しさを感じたり、...

本講義では、リズムを処理する脳の不思議について、皆様と共に、探究してみたいと思います。私自身、ドラマーとしてリズムを演奏します。そのリズム演奏の感覚の中には、宇宙の感覚があります。その感覚を脳科学の観点から眺めてみると...
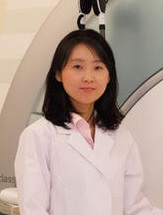
本講義では、量子力学の原理を応用した認知科学の新しいモデルである「量子認知」の基礎とその応用を紹介します。従来の古典的確率論では説明が難しい意思決定や信念更新、認知バイアスなどを、量子確率論を使って理解することができるよ...

主体性とは一般に「自らの判断と意志とに基づいて対象に働きかけ、目的を実現し、さらにその結果についての責任を負おうとする態度」のことを指すが、脳科学的には、外界や他者と関わる複数の脳機能の総合によって形成される複雑な現象と...
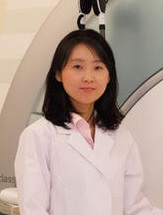
偏ったものの見方や思い込みなどの「認知バイアス(認知の歪み・錯覚)」は、これまで、認知科学、社会心理学、行動経済学において研究が続けられてきました。認知バイアスは、外界の刺激などに対して脳内で独自に創造された「主観的経験...

スポーツに熟達するには、単に身体(筋力やフォームなど)を鍛えれば事足りるものではない。試合の重大な局面で持てる技能を最大限発揮するためには、心身の状態を最適化する必要がある。また、とりわけインタラクティブな競技では、ボ...