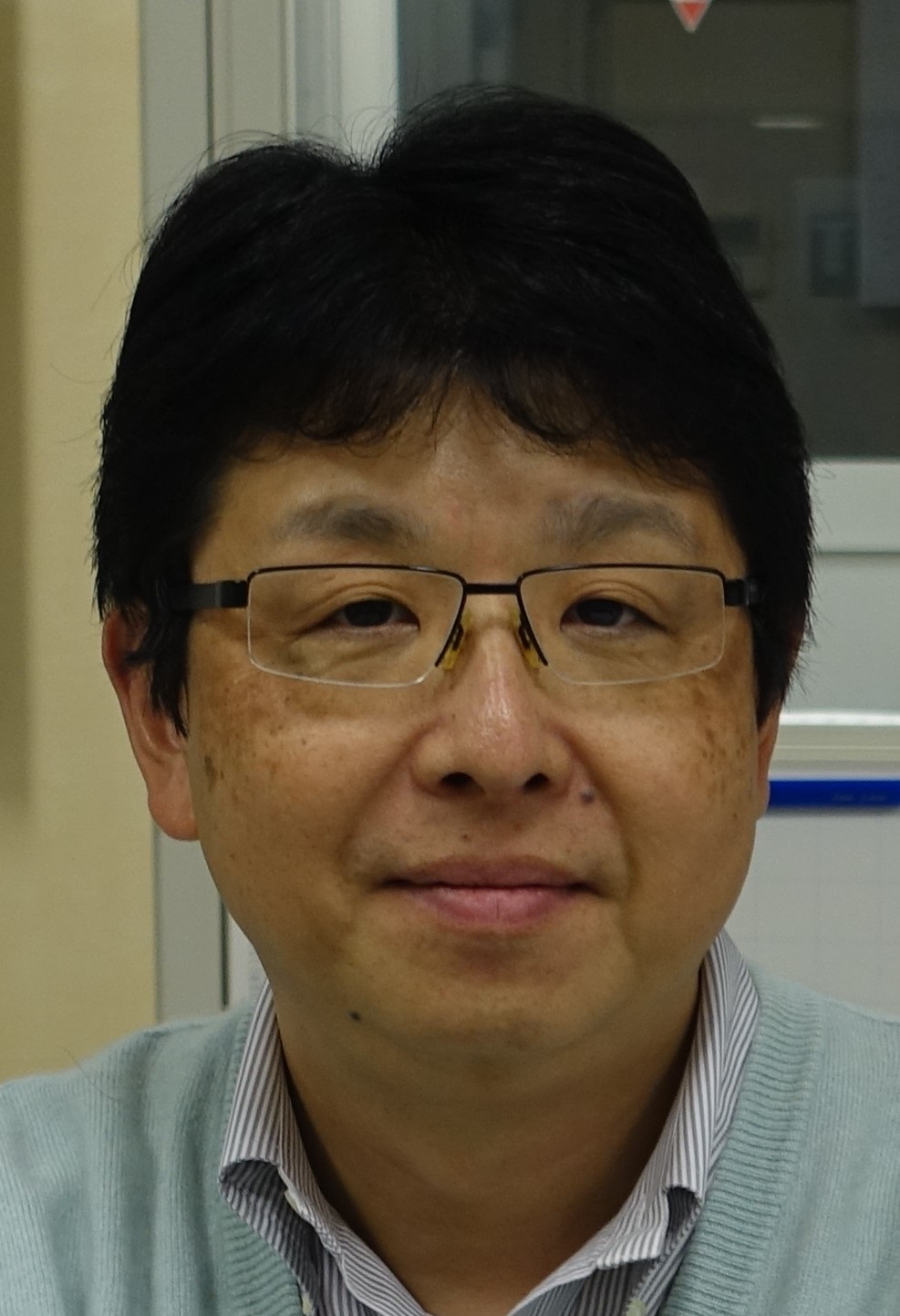
質感工学と五感工学の基礎と応用:岡嶋 克典(横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授)
私たち人間は五感(視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚)を通して外界の情報をリアルタイムに収集しており、脳はそれらの情報を基に次の行動を決定しています。五感の中でも視覚は生活する上で重要な情報を提供していますが、私たちは視覚情報...
応用脳科学アカデミー
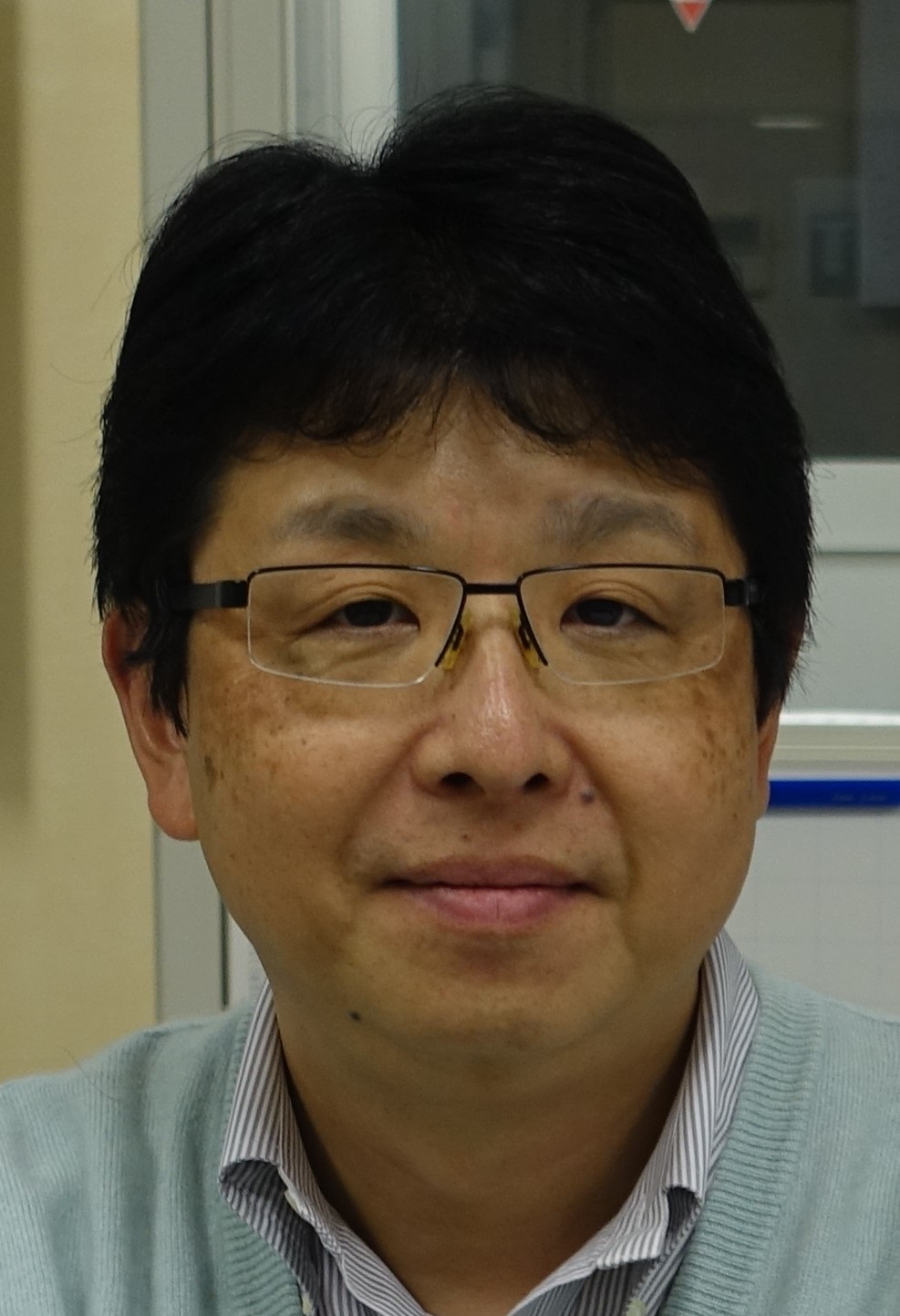
私たち人間は五感(視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚)を通して外界の情報をリアルタイムに収集しており、脳はそれらの情報を基に次の行動を決定しています。五感の中でも視覚は生活する上で重要な情報を提供していますが、私たちは視覚情報...
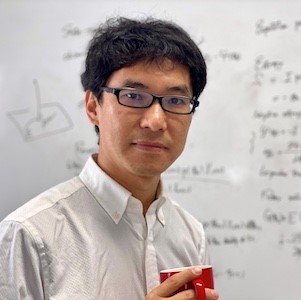
本講演では脳の自由エネルギー原理が形成されてきた歴史的背景を,それを支える主要な実験結果や他分野との関わりとともに紹介する.自然刺激への適応に基づく古典的な認識の理論から,外界のモデルを脳の中に持つとするベイズ脳仮説,そ...

「時間があっという間に過ぎた」「タイミングが良い」といった言葉をよく耳にするように、「時間」は我々が日常生活を営む上で非常に身近な存在です。そして私達は時々刻々と変化する環境に対して適応的に行動するために、物事の起こるタ...

脳のさまざまな機能を統一的な視点から説明する理論として,Karl J. Fristonが提唱している自由エネルギー原理が近年注目を集めています.この理論では,変分自由エネルギーと呼ばれる量を核として,それをさまざまな形に...

私たちは日々、目的を持って行動している。いろいろな状況に応じて、どのように具体的な行動が生み出されるのか、その仕組みにはまだまだ分からないことが多い。しかし、行動が脳により生み出されている以上、脳内の神経活動の中には、個...

音楽療法の効果については,従来の逸話的・主観的なものから,科学的・客観的なデータによる評価に移りつつある。脳神経疾患のなかで現時点で音楽療法の有効性が確認されているものとして,認知症の behavioral and p...

ヒトが外界から受ける感覚情報を処理するとき、刺激を感覚器官によって受容し、それらを総合的に意味づけし、経験や記憶に基づいて解釈をおこなう過程を経ます。五感情報ディスプレイはこうした感覚情報の流れを修飾し、編集するものであ...

現行の精神障害の診断分類は、患者自身の主観的報告と医師による行動観察に基づいており、生物学的知見・病因・病態生理に基づいた体系になっていない。また、近年の生物学的知見の蓄積によっても、診断、重症度評価、予後や治療反応性予...

ヒトは食品を咀嚼・嚥下する際に、口腔内に放出される呈味・香気成分を味覚・嗅覚(化学感覚)情報として検知するとともに、歯ごたえや舌触りといった食感を触覚・聴覚(物理感覚)情報として検知しており、見た目の視覚情報も加え、これ...

現在、機械学習の中心となっている深層学習(ディープラーニング)は、高精度であるものの説明性が極めて低く、処理の判断根拠や機序を人が理解することが困難であり、産業界への導入の妨げになっています。深層学習の説明性を高めること...